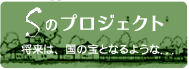日本のすがた・かたち
 茶をのめば自ずと知れることもあり
茶をのめば自ずと知れることもあり
うましといえる我も知るかな
お茶を掬う匙のことを茶杓(ちゃしゃく)といいます。
桃山時代の16世紀末、千利休によって成された「侘茶(わびちゃ)」はその後の日本文化のかた・かたちに大きな影響を与えました。八代将軍足利義政が儀礼化した茶礼は150年余りで大きく様変わりし、唐様といわれるものから和様と呼ばれる新興の茶の湯に変化を遂げました。利休はその立役者といわれます。
利休は茶会ごとに手作りの道具を出して客を持て成したといわれ、その中で身近なものは茶杓と蓋置(ふたおき)という竹製のものでした。蓋置きは高さ54ミリほどの、釜の蓋を置くものということからその名が付いていますが、ここには湯を汲む竹の柄杓も置き、果ては音をたて、その合図で一同が挨拶をするなど、中々重要な小物です。
私も茶事、茶会ごとに茶杓と蓋置を作ります。削りながら当日来られるはずの客の顔を思い浮かべ、どう見てくれるだろうか、作りがいいといってくれるか、などと思いを巡らせます。作っている時の楽しさと味わいは茶会で使うその時より数段上のような気がしています。
なぜ、利休たちは茶杓を手作りにしたのか。その訳は削り使ってみると理解できます。物語性を孕んだ竹の一片は、その茶会の主役になる可能性を秘めています。
人を持て成すことは和心をもってすべし、と先人は説いています。
その2時間のために心をこめて準備をし、客もそのままの有様でその場に臨む。何事によらず先人が好んできた精神の在り方です。それは能舞台の演者と見所(けんじょ・客)のように、意識を研ぎ澄ました者同士が、相まみえる舞台のようです。
多種多様な国の文化をひとつの茶碗に入れ、それを竹の茶筌(ちゃせん)で混ぜ練り回して喫む一服の茶。日本人の見事な味覚と養生法と、強靭な胃袋の文化消化酵素を目の当たりにする光景です。
今、近く催される茶会用の茶杓を削りながら、何という銘をつけようかなどと思いを巡らせ、胸躍らせています。